
- 専門性を高めたいけど、認定看護師になる方法が具体的にわからない
- 資格を取るまで大変そうで、費用や期間も気になる
認定看護師は広く知られた専門資格ですが、資格保有者は看護師全体の約1〜2%と少なく、多くの医療機関から求められています。認定看護師になるには、実務経験や専門分野での経験、教育課程の終了など多くのハードルをクリアしなければなりません。
この記事では認定看護師になるためのステップや費用、分野選びのポイントを詳しく解説します。記事を読むと資格取得への具体的な道筋がわかり、将来の可能性が広がります。認定看護師になる流れを把握して、自分の専門性を高める一歩を踏み出しましょう。
認定看護師になるまでの流れ

認定看護師になるには、以下の流れが一般的です。
- 正看護師の免許を取得する
- 実務経験が通算5年以上、うち3年以上は希望分野での経験を積む
- 厚生労働省が指定する教育機関で6か月間(615時間以上)の教育を受ける
- 修了後、日本看護協会が実施する認定審査に合格する
1.正看護師の免許を取得する
認定看護師の受験資格を得るためには、正看護師(看護師)の免許取得が必須です。正看護師になるためには、以下のいずれかの教育機関を卒業しなければなりません。
- 看護専門学校(3年制)
- 看護系短期大学(3年制)
- 看護系大学(4年制)
上記の教育機関で学び、年に1回(2月)実施される看護師国家試験に合格すると免許を取得できます。合格率は例年90%前後と高いですが、試験に向けた準備は必要です。すでに准看護師として働いている方は、2年生の進学課程(通信制も含む)を修了すると、国家試験の受験資格を得られます。
2.実務経験が通算5年以上、うち3年以上は希望分野での経験を積む
認定看護師の資格取得には、実務経験が通算5年以上、そのうち希望する認定分野での経験が3年以上必要です。基本的な看護技術に加え、希望分野での実務経験は特定の分野での専門性を証明するために欠かせない要件です。原則としてフルタイム(常勤)勤務が基準で、パートタイム勤務の場合は勤務時間に応じた経験年数が換算されます。
認定看護師申請時には、勤務先からの実務経験証明書が必要です。単に年数を満たすだけでなく、研修への参加歴や特定のケア経験などもアピールポイントになる場合があります。認定看護師を目指すなら目標分野を明確にし、計画的に必要な実務経験を積みましょう。
3.厚生労働省が指定する教育機関で6か月間(615時間以上)の教育を受ける

認定看護師の取得過程では、厚生労働省が指定する教育機関で6か月間(615時間以上)の教育を受ける必要があります。認定看護師に必要な専門知識や技術を体系的に身に付ける必要があるためです。入学には筆記試験や面接があるため準備が必要です。認定看護師の教育課程では、以下の内容を学びます。
- 共通科目:看護管理や臨床薬理学、フィジカルアセスメント
- 専門科目:選択した認定分野に特化した知識・技術
認定看護師の教育は講義だけでなく演習や実習も含まれます。教育課程中は休職して学びに専念する必要がありますが、eラーニングを導入している教育機関では在職中の受講も可能です。奨学金制度の有無も事前に確認しておきましょう。
4.修了後、日本看護協会が実施する認定審査に合格する
認定看護師の教育課程を修了した後は、日本看護協会が実施する認定審査に合格する必要があります。試験では選択した専門分野の知識や実践的な判断力が問われます。認定審査は年に1回の筆記試験形式で、合格には7割程度の正答が必要です。
受験前には、申請書を提出し約3万円の受験料を支払います。合格後は約2万円の認定登録料を納付すると認定証が交付されます。認定資格は5年ごとに更新手続きが必要なので、注意してください。
認定看護師になるための費用

認定看護師になるために必要な費用について以下の2点を解説します。
- 教育課程の受講費用は約50〜100万円
- 期間中の生活費や交通費は自己負担
教育課程の受講費用は約50〜100万円
認定看護師の教育課程の受講費用は、国公立は約50万円前後ですが、私立や大学附属では80〜100万円程度かかります。テキストや教材費、遠方の場合の宿泊・交通費も別途準備が必要です。
多くの病院では、受講費用の負担を軽減するために研修制度や奨学金制度を設けています。日本看護協会による、認定看護師教育課程修了者向けの補助金制度も利用できる場合があります。受講中は収入の減少も予想されるため、事前に資金計画や支援制度を確認しておきましょう。
期間中の生活費や交通費は自己負担
認定看護師の教育課程中は生活費や交通費が自己負担となり収入も減ることが多いため、事前の資金計画が重要です。自己負担となる主な費用は以下のとおりです。
- 生活費
- 住居費(遠方の場合)
- 教育機関への往復交通費
- 教材費や参考書代
- 認定試験の受験料(約3万円)
教育課程中の経済的負担に備えて十分な貯蓄を準備しましょう。勤務先の病院や日本看護協会に奨学金制度がないか確認してください。認定登録料の交付や、認定後の更新費用も考慮した資金計画を立てておくと安心です。
認定看護分野の種類と特徴

認定看護師は専門分野ごとに特化した役割を持ち、患者や医療現場のニーズに応じて活躍しています。以下に代表的な4つの分野とそれぞれの特徴を紹介します。
- 感染管理:院内感染の予防と対策を担う
- 緩和ケア:がん患者への痛みや苦しみの軽減を支援する
- 集中ケア:ICUで重症患者に対応する
- 認知症看護:認知症高齢者のケアと家族支援に特化する
» 看護職の種類と役割を徹底解説!
» 看護師の仕事内容|勤務先や給与もまとめてチェック!
感染管理:院内感染の予防と対策を担う
感染管理認定看護師は、院内感染対策の最前線で活躍する専門家です。主な業務は以下のとおりです。
- 手指衛生の徹底と指導
- 感染経路別の予防策確立
- 抗菌薬の適正使用推進
- 医療器具関連の感染予防対策
- 環境整備と清掃方法の管理
感染管理認定看護師は感染対策チーム(ICT)の中核として、感染症発生データを分析し効果的な対策を立案・実施します。アウトブレイク発生時には迅速に対応の指揮をとり、医療従事者への教育・指導を通じて病院全体の感染レベルを向上させます。近年、感染管理認定看護師の重要性は高まっており、医療安全の最前線で活躍する分野です。
緩和ケア:がん患者への痛みや苦しみの軽減を支援する
緩和ケア認定看護師は、以下の専用スケールを使用し、客観的に状態を把握します。
- CDS (Cancer Dyspnea Scale):呼吸困難感を評価
- CES (Care Evaluation Scale):緩和ケアにおけるケアプロセスを評価
- RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale):鎮静度を評価
- IPOS (Integrated Palliative care Outcome Scale):緩和ケアの質を評価
薬物療法と非薬物療法を組み合わせ、痛みの管理では医療用麻薬を適切に使用し、副作用対策も行います。患者の心理的ケアと並行して家族への精神的サポートも、緩和ケア認定看護師の重要な役割です。認定看護師は医師や薬剤師、ソーシャルワーカーなど他職種と連携してチームアプローチも実施します。
終末期には意思決定支援や倫理的問題への対応、在宅ケア移行支援、地域医療機関とも連携します。
集中ケア:ICUで重症患者に対応する

集中ケア認定看護師は、ICUにおいて生命の危篤状態にある重症患者を24時間体制で管理するスペシャリストです。呼吸や循環、意識に問題を抱える患者に対し、人工呼吸器や血液浄化療法など高度医療機器を扱います。集中ケア認定看護師には急変時の迅速な判断力、複雑な病態理解、鋭い観察力が欠かせません。
集中ケア認定看護師はバイタルサインに加え、患者の表情や皮膚状態など微細な変化にも注意を払います。患者の尊厳を守る倫理的判断力や不安を抱える家族への精神的サポート、他職種との効果的な連携能力も重要です。ICU退室後のリハビリテーション計画にも関与し、チーム医療の要として患者の救命と回復を支えています。
認知症看護:認知症高齢者のケアと家族支援に特化する
認知症看護の認定看護師は、認知症高齢者の尊厳を守りながら一人ひとりを大切にするケアのエキスパートです。認知症看護の認定看護師の主な役割は以下のとおりです。
- 認知症の進行度に合わせた個別ケア
- BPSDへの非薬物的介入
- パーソンセンタードケア
- 家族介護者へのサポート
認知症看護の認定看護師は医師や介護職、作業療法士と連携し、患者の権利擁護と意思決定を支えます。家族介護者へのサポートも重要な役割です。認知症看護の認定看護師は高齢化社会で需要が増え、早期発見や予防、若年性認知症支援などで活躍しています。
認定看護師を目指す際の注意点

認定看護師を目指す際は、以下の点に注意しましょう。
- 職場の理解と協力を得る
- 教育課程中は収入が減る場合がある
- 将来のビジョンを明確にする
- 認定資格は5年ごとに更新が必要になる
職場の理解と協力を得る
仕事を続けながら資格取得を目指すなら、職場の理解と協力は重要なポイントです。上司や同僚には早めに資格取得の意向を話し、具体的なスケジュールを伝えます。人事部や上司に相談すれば、勤務シフトも調整してもらいやすくなります。
認定看護師の資格を持つ先輩看護師がいる場合は、アドバイスをもらうのも有効です。自分の学習の様子を定期的に職場で共有するのもおすすめです。勉強に取り組む姿を理解してもらい支援を受けましょう。
教育課程中は収入が減る場合がある
認定看護師の資格取得には約6か月間の教育機関への通学が必要なため、原則として休職か退職が求められます。教育課程中は完全休職か時短勤務、退職のいずれかを選択するのが一般的で、収入は減少します。
職場環境によっては、有給休暇の活用や時短勤務制度を利用できる場合もありますが、多くは収入面での調整が必要です。教育課程中の経済負担に備えるためには貯蓄計画を立て、助成金や奨学金制度を確認します。研修費補助制度を設けている医療機関もあるため、所属施設の支援制度を早めに調べておきましょう。
資格取得後は給与アップや専門手当の支給がある職場も多くあります。一時的な収入減少は発生しますが、将来の収入増加につながる自己投資として捉えることが大切です。
将来のビジョンを明確にする

認定看護師へのモチベーションを維持するためにも、将来のビジョンを明確にしましょう。どの分野でスペシャリストになりたいかを考え、キャリア計画を立てます。長期的な計画を立てる際は、ワークライフバランスも考慮してください。
多くの施設では認定看護師に対して手当が支給されますが、金額は施設によって異なります。自分の専門性を生かし、後進の育成や地域医療のレベル向上に携わるなど、活躍の場を広げましょう。明確なビジョンを持つと、教育課程中の苦労や資格取得後の責任の重さを乗り越える力が得られます。
認定資格は5年ごとに更新が必要になる
認定看護師の資格は取得して終わりではなく、5年ごとに更新手続きが必要です。更新のためには以下の条件を満たす必要があります。
- 所定の継続教育研修
- 実践活動の証明
- 更新申請
- 審査料(約3万円)
更新申請は、資格の有効期限の約6か月前から受付が始まります。職場の異動や育児休暇を取得している場合でも更新する必要があります。資格が失効した場合は、再度認定審査から受け直す必要があるため注意してください。
認定看護師を目指す際によくある質問
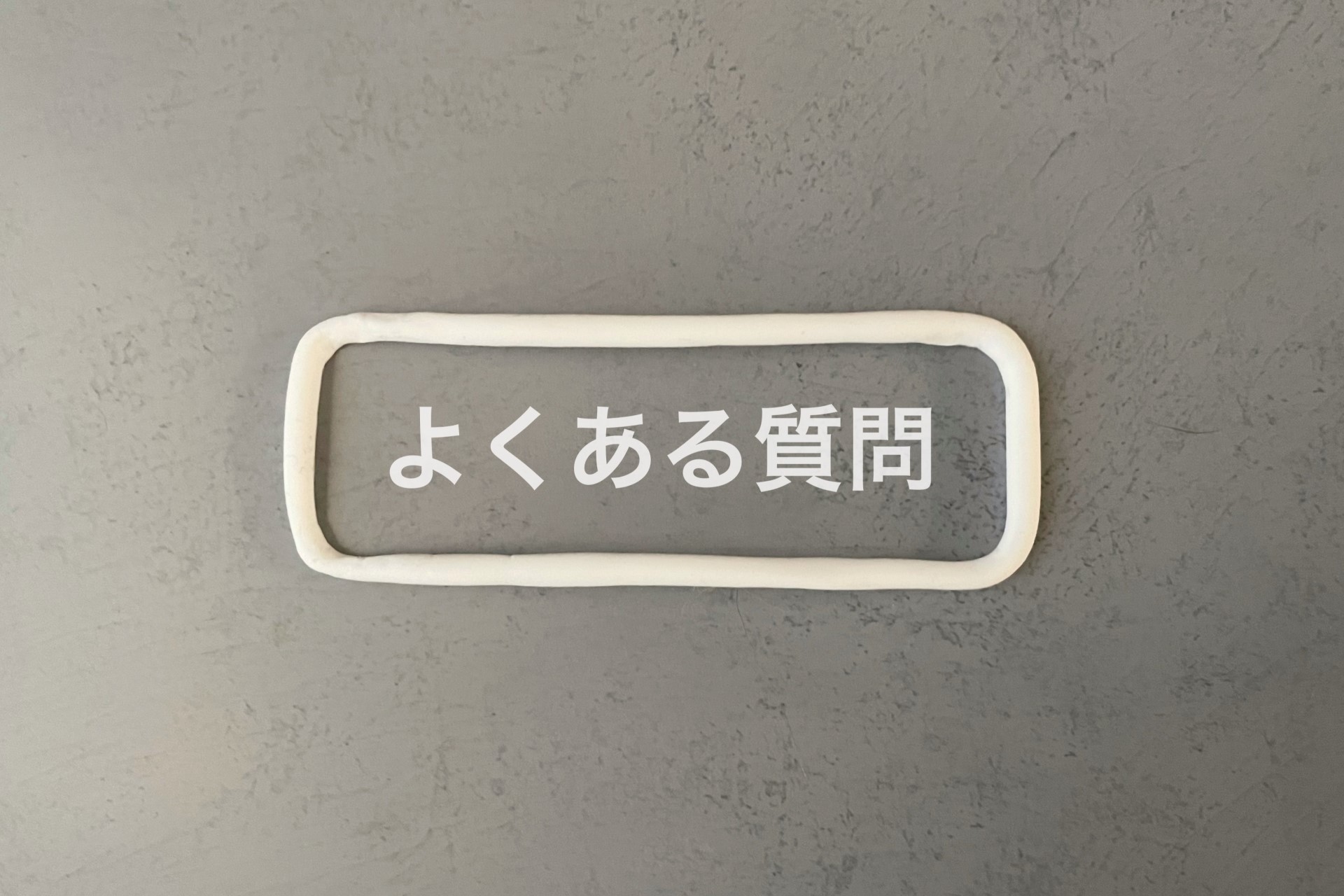
認定看護師を目指す際によくある質問を以下にまとめました。
- 認定看護師資格の難易度はどれくらい?
- 認定看護師資格が役立つ職場は?
- 認定看護師の需要は増えている?
認定看護師資格の難易度はどれくらい?
認定看護師資格の難易度は試験の合格率だけ見ると約90%で、比較的取得しやすい資格です。しかし615時間以上の専門教育課程や実習、厳しい受験資格があります。取得後も5年ごとの更新が必要で、資格維持には継続的な学習や実践が欠かせません。
教育課程の学習では研修中の多数のレポートや課題、専門知識の習得、実習でのスキル向上が求められます。働きながら学ぶ場合は時間管理と体力面での負担が大きいため、計画的な準備と強い意思が不可欠です。
認定看護師資格が役立つ職場は?

認定看護師資格は多岐にわたります。主な活動の場は以下のとおりです。
- 総合病院や大学病院
- 専門的な診療科
- 訪問看護ステーション
- 介護施設
- 地域包括支援センター
- 保健所や行政機関
- 教育機関
感染管理認定看護師は院内感染対策チームの中核として、緩和ケア認定看護師はホスピスや在宅医療の現場で活躍します。医療機器メーカーや製薬会社の民間企業、災害医療支援チーム、医療コンサルティング会社でも専門知識を生かした職務が可能です。教育機関での育成役として活躍する道も開かれています。
認定看護師の需要は増えている?
認定看護師の需要は確実に増加しています。高齢化社会と医療の高度化により、専門知識を持つ看護師の必要性が高まっているためです。需要が高い分野は以下のとおりです。
- 感染管理
- 認知症看護
- 緩和ケア
- 皮膚・排泄ケア
認定看護師の配置が診療報酬の加算要件となっている分野もあり、医療機関側の採用ニーズも増加しています。COVID-19パンデミック以降は、感染管理認定看護師の重要性が高まりました。転職市場での評価も高く、地方の中小病院でも認定看護師を積極採用する傾向があります。今後も認定看護師の需要は増加する見込みです。
まとめ

認定看護師になるには、正看護師免許の取得後、実務経験5年以上(希望分野で3年以上)が必要です。その後、6か月間の専門教育機関での学習を経て認定審査に合格すると、認定看護師になれます。教育費用は50〜100万円程度と高額ですが、専門性を生かした活躍の場が広がることは将来のキャリアを後押しします。
専門分野は、感染管理や緩和ケア、集中ケア、認知症看護など多彩です。専門性はキャリアを大きく広げ、患者に寄り添うケアなどやりがいも感じられます。高齢化社会で需要が高まる専門看護師として、医療現場での活躍がますます期待されています。
» 認定看護師と専門看護師の違いを徹底解説
将来の目標に向けて一歩ずつ準備を進め、理想の看護師像を実現しましょう。